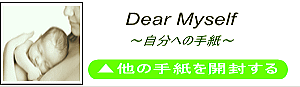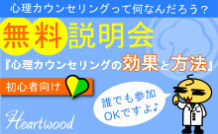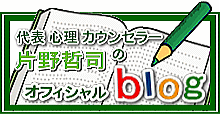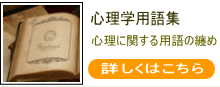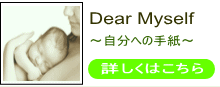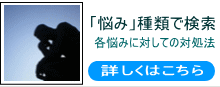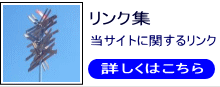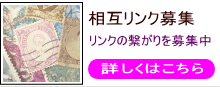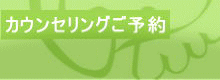東急東横線 (渋谷〜横浜) 川崎市・元住吉駅の心理カウンセリングルーム。ハートウッド心理カウンセリングです。
電話でのご予約・お問い合わせはTEL.044-572-7199
| サイトマップ | プライバシーポリシー |
勧酒 「サヨナラ」ダケガ人生ダ
『酒を勧む』
この杯を受けてくれ
どうぞなみなみ注がしておくれ
花に嵐のたとえもあるぞ
「さよなら」だけが人生だ
五言絶句
この詩は井伏鱒二氏の訳詩集『厄除け詩集』に掲載されています。この詩の基になったのは中国は唐の時代、詩人である于 武陵(う ぶりょう810−)によって作られた五言絶句です。五言絶句とは五言(五つの漢字)が絶句(四句、四つの行)で表している構成のを言います。原文は以下のようになっています。『勧酒』
勘 君 金 屈 巵 君に勘める金屈巵(きんくっし)満 酌 不 須 辞 満酌(まんしゃく)辞するを須(もち)いず
花 發 多 風 雨 花發(ひら)けば風雨多く
人 生 足 別 離 人生別離足(おお)し
私たちは人と触れ合い、そして別れのときを迎えなければいけません。卒業、引越し、進学、転勤、留学、もしくは死別、私たちは今まで多くの別れを経験したかと思います。お互いの道を分かち合いそれぞれの道を選んだ人も、喧嘩別れをし今でもその関係を引きずっている人も、誤解を解けずに後悔した別れを経験した人も、言いたいことを言えずに心苦しい思いをした人もいるでしょう。
良い別れもあれば当然の悪い別れもあります。その中で後悔しない別れを迎えるには、別れを避けるよりも別れを感じ取るのが必要なのかもしれません。人生とは出会いがあって別れがあるのではなく、出会いの中には既に別れが存在しているもの。だからこそ突然訪れるかもしれない別れの受け入れが大切なのだと思います。
別れを否定することは出会いまでも否定してしまうことではないでしょうか。永遠に続くものはありません、人との関係だって繋がってはいても常に変化し続けています。もしお互いが出会えたなら、その関係を存分に感じ取り喜びに満ち溢れましょう。一つの出会いはその場その時以外もう二度と訪れはしないのですから。
『勘酒』とは、まさに「一期一会」を表している詩だと思います。
現代語訳として(失礼ながら)次のように意訳させて頂きました。
『どんなに美しい花が咲いたとしても一時の嵐によって散ってしまう様、とにかく物事には邪魔が起こりやすい。別れは決して避けることはできず、いずれ訪れてしまう。だからこそ、今ここでの時間を大切にし感謝をしよう。さあこの杯を取って祝福を挙げようではないか。』
<追記>
またこの「勘酒」を受け、詩人、劇作家である寺山修司氏は以下のような二つの詩を残しました。とても悲観的な詩ではありすが、別れについて異なる側面から大切にしているからなのかもしれません。この二つの詩をセットに感じてみると山寺修司氏のさよならに対する優しさが一段と伝わる気がします。こちらを最後に記載させて頂きます。
『さよならだけが人生ならば』
さよならだけが人生ならば また来る春は何だろう
はるかなはるかな地の果てに 咲いている野の百合何だろう
さよならだけが人生ならば めぐり会う日は何だろう
やさしいやさしい夕焼けと ふたりの愛は何だろう
さよならだけが人生ならば 建てた我が家は何だろう
さみしいさみしい平原に ともす明かりは何だろう
さよならだけが 人生ならば
人生なんか いりません
『だいせんじがけだらなよさ』
さみしくなると言ってみる ひとりぼっちのおまじない
わかれた人の思い出を わすれるためのおまじない
だいせんじがけだらなよさ だいせんじがけだらなよさ
さかさに読むとあの人が おしえてくれた歌になる
さよならだけがじんせいだ さよならだけがじんせいだ