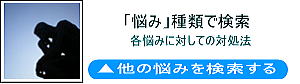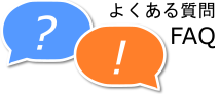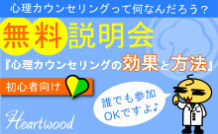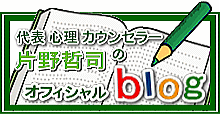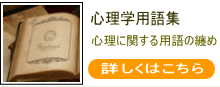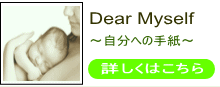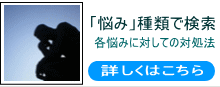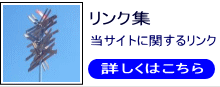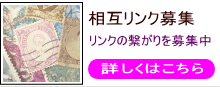東京・神奈川(横浜・川崎)で活動している心理カウンセリングルーム
電話でのご予約・お問い合わせはTEL.044-572-7199
| サイトマップ | プライバシーポリシー |
歪んだ考えDistorted Cognition
考えたくもないことを考えてしまい悩まされている方へ
- 良くないことばかり考え余計な不安を感じてはいませんか?
- 主観的になりすぎ現実的でなくなることはありませんか?
- 特定の場面でいつも同じような考え方に陥り嫌な感情を引き起こしていませんか?
人の思考にはパターンがあるものだと思います。あなたの培ってきた思考のパターンはどこからやって来て、どの様にあなた自身を支えているのでしょうか。特定の思考パターンは良くも悪くも生活の中での特定の行動パターンへと繋がり、特定の感情パターンも引き起こすものです。思考と行動と感情は密接な相互関係にあるのです。その中のどれがきっかけになるか、どれが重要かは特定できるものではありません。
ここでは思考に焦点を当てて話を進めていきます。
認知の歪み(by 認知行動療法)
心理カウンセリングの分野から、偏った考え方に陥ることを「認知の歪み」と呼びます。日常生活の中で代表される認知の歪みを挙げます。あなたの傾向に当てはまる項目はありませんか?参照してみてください。- 全てか無か思考:物事を白か黒かと極端な二極化でしか捉えない傾向。
- 一般化のしすぎ:一つの良くない事件が起ると、その他の全てが良くないと決め付ける傾向。
- 心のフィルター:ほんの一部分の良くない事柄にしか意識が向かない傾向。
- マイナス化思考:常に駄目な部分に目を向けてしまう傾向。
- 結論の飛躍:根拠に関係なく原因に関しての過程を飛び越え結論を導き出す傾向。
A)心の読みすぎ:今までの経験から勝手に相手の感情を決め付けてしまう傾向。
B)先読みの誤り:今後の未来を悲観的に感じ取ってしまう傾向。 - 拡大評価と過小評価:自分の失敗や短所を過大に、成功や長所を過小に評価してしまう。
- 感情的決め付け:自分の感じたことが一般常識として捉えてしまう傾向。
- すべき思考:行動の原動力が”WANT”ではなく責任や義務の”MUST”で急き立ててしまう傾向。
- レッテル貼り:「私はどうせ〇〇だから」と決め付け、問題の原因や過程に背を向ける傾向。
- 自己関連付け:自分にとって関係のない事柄に対してまで罪の意識を感じてしまう傾向。
認知思考の変化への対策
歪んだ認知とは偏った側面からしか物事を判断できなくなる傾向に有ります。多面的な側面から物事を判断できる円滑な認知が必要とされます。その為に一度感情と行動を関与させ認知の有り方を振り返ってみてください。以下の7つの質問過程に沿って答えてみてください。
Step 1:出来事
いつ、どこで、誰と、何が、どの様な出来事が起こりましたか?なるべく具体的に何が起ったかを振り返ってみてください。
Step 2:感情
その時にどのような感情が引き起こされましたか?【感情の種類―割合(0 – 100%)】を幾つか思いつく感情を挙げてみてください。(身体的反応があればそちらも意識してみましょう。)
Step 3:歪んだ認知
上記の認知の歪みからどの様なパターンがこの事例に当てはまりますか?参考にしてみてください。どの歪んだ認知がより強く現れていると感じますか?
Step 4:反論
ストップ!一度冷静になってみましょう。歪んだ認知に対する現実的な反論はどのようなものですか?客観的事実にのみ焦点を合わせ違った側面から冷静に反論してみましょう。
Step 5:反論に対する裏付け
歪んだ認知に対する現実的な反論を裏付ける証拠はありませんか?ここでは反論のみに味方になった促しをしてみてください。
Step 6:適応的思考
歪んだ認知と現状のバランスを図るとしたらどの様な結論を出しますか?主観的な感情と客観的な事実を中立な立場で判断してみてください。
Step 7:感情の変化
最終的にはどの様な感情が残りましたか?出来事に関連した感情に対して何か変化はありませんか?【感情の種類―割合(0 – 100%)】をもう今一度校了してみてください。どの様に変化しますか?
いかがですか?文章にして考えてみるとややこしいかもしれませんね。
カウンセリングではこのような内容をカウンセラーがガイドしながら進む場合もあります。マニュアル通りにはいかないクライアントの心の有り方とペースに添って臨機応変に進めていきますのでどうぞご安心くださいませ。